「哲学たいけん」のために
「哲学たいけん」は可能なのか
哲学それ自体は、ひとつの、しかも特殊な学問である。その哲学という学問は、一般の人たちにも体験可能なのか。これは、わが「哲学たいけん村」にとっては、基本的な問いである。なぜなら、もしも哲学が一般の人たちには体験できない学問ならば、広く世間に開かれた形で構想された「哲学たいけん村」そのものが、はじめから無意味になってしまうからだ。
逆に、もし体験できるとしても、哲学のどのような面で、どのような意味で、「哲学たいけん」が可能なのかを、はっきりさせておかねばならない。
そのためには、先ず、「たいけん」(体験)が他のさまざまな経験とどう違うかについて、次いで「哲学」が他のさまざまな学問とどう違うかについて、述べておくべきであろう。
「たいけん」
私たちの生活は経験の連続であると言ってもいい。なにかを見たり、聞いたり、なにかに触れたりするのも、経験である。街を歩くのも、室内で仕事をするのも、食事をとるのも、眠るのも、経験である。ほとんど無意識的な経験もあれば、はっきり意識しての経験もある。誰かがなにかを教えこもうとして私たちに仕向けるような経験もあれば、また、私たちがなにかを学ぼうとして、自分の方から求めるたぐいの経験もある。なにかを経験しても、すぐに忘れてしまったり、はじめは覚えていても、いつの間にか記憶から去ってしまったり、あるいは逆に、いつまでも忘れられなかったり、忘れているようでも、不意に思い出したり、経験の深さ、あるいは重さも、さまざまである。
そのさまざまな経験のなかでも、自分の心の深いところで受け止められ、自分自身の考えかた、生きかたになんらかの影響を与えるような経験、自分の人生にとってなんらかの意味を持つたぐいの痕跡を心に残すような経験を、とくに他のいくつもの経験から区別して、「体験」[Erlebnis]とよぶ。
とすれば、人それぞれが心の深みで、自分自身にかかわる事柄として哲学を体験できるかどうかが、「哲学たいけん村」の成否のわかれめになってくる。
「哲学」
では、はたして哲学は、一般の人たちにとっても、自分自身にかかわる事柄たりうるのだろうか。
たしかに、哲学それ自体は、ひとつの、しかも特殊な学問ではある。しかし、哲学が追求しようとしている真理は、実は、人間として生きているすべての者にとって、だから一般の人たちにとっても根本的な事柄、自分自身の存在の根幹にかかわるような事柄なのである。その自分自身の根幹にかかわるような事柄は、決して、その全部を外部にさらけ出して見せることはできない。客観化し対象化しきることはできない。
一般に学問とは、真理の追究である。それぞれの学問が、それぞれの学問上の真理を追究しつづけている。そして、その真理は、いつでも、どこでも、誰にとっても通用するはずの真理として、客観的に証明された形で主張されるのが、そして、もしその証明に間違いがあれば、もはや真理たりえないというのが、いわば常識である。その常識は、それぞれの分野での客観的な、普遍的な真理の追究こそが学問の使命だと認めることを、前提としている。
ところが、哲学の場合は、必ずしもこの常識どおりには行かない。哲学の追求する真理は、客観的証明を必要不可欠な条件とはしない。それは、むしろ、人が主体的に納得すべき真理 である。
だから、哲学的な真理は、客観的な知識としてよりも、主体的な思想として主張されることになる。思想は本来、客観的であるよりは、主体的なものであり、主体的なものは客観化しつくせないからだ。そして、思想については、つねに、それが誰の思想かが問題になる。知識は万人にとっての知識であるべきだが、思想には万人の思想などというものはない。思想は、人それぞれの主体によってのみ、主体においてのみ生きる。
もちろん、哲学にとっても知識は必要である。客観的な知識、とりわけ哲学史上の客観的知識を無視して、哲学的な思想を主張することはできまい。しかし、知識をいかに積み上げてみても、それだけでは思想にはならない。その点でも、哲学は特殊な学問である。世間から哲学の専門家と思われている人たちの大部分は、実は哲学史家、つまり哲学でなく哲学史の専門家にすぎず、哲学史に名を留めている個人の思想についての知識を積み重ねているだけか、その種の知識を切り売りしているだけであって、自分自身の体験に裏付けられ、自分自身の思想として形成された哲学を持ってはいない。
その自分自身の思想としての哲学を裏付けるべき体験という面で、また、おそらくその面でのみ、「哲学たいけん村」の意図する「哲学たいけん」の地平が開ける。体験はまぎれもない自分自身の主体的な体験であって、他人の体験ではない。その自分の体験を大切にしながら、しかもその体験をもとに自分自身で考えることを始めたとき、その人はもう哲学の入り口にいる。それが、「哲学たいけん村」の村民の資格でもある。
「哲学」的な「たいけん」
できあがった思想体系だけが哲学のすべてではない。哲学者が自分自身の思想を形成するきっかけ、あるいは推進力になっている体験を、どのように自分の思想のなかに生かしていくかも、哲学の枠内の問題である。
隙間なく緻密に、理詰めに形成された体系だけを哲学だと思うのは、間違いである。それよりも哲学にとって先ず必要なのは、哲学的な問題意識が体験のなかから芽生えることである。そして、哲学的な問題意識につらなるような体験それ自体は、無論、決して理詰めのものではありえない。理性的であるどころか、きわめて感性的なものだ。感性を欠いた哲学などというものは、存在しない。むしろ、哲学的な問題意識を抱くことのできるような感受性を磨くことが、哲学の第一歩なのだ。それなくしては、哲学的な体験もありえない。
哲学という学問が始まったのは古代ギリシアにおいてだったが、この学問の名前は、もともとギリシア語では「知を愛すること」、「知恵への愛」を意味した。愛も、断じて理詰めのものではない。philosophia(哲学)は、感性と密接に結び付いている。
そのことをはっきりさせるために、ここで哲学的な体験たりうるものを、大雑把に3つにわけて取り上げておきたい。第一に驚き、第二に疑い、第三に不安である。
驚き
「不思議に思うこと、この感情は哲学者のものである。哲学には、これ以外の起源はない」と、古代ギリシアの哲学者プラトンは言った(プラトン『テアイテトス』)。この不思議に思う感情を、「驚き」とよんでもいい。その驚きの対象は、なにも、誰もがびっくりするような奇怪なものでなくてもいい。むしろ、誰も不思議に思わないような、ごくありふれた事物についても不思議に思う、驚くというような感受性が、哲学には必要なのであり、その驚きとともに哲学が始まるのだ。
プラトンと同じく古代ギリシアを代表するもうひとりの哲学者アリストテレスが、こんなことを言っている。「なるほど私たちの知識の原初的な源ではあるが、しかし私たちに決して、なぜ何かがかくあるのか(たとえば、なぜ火は熱いのか)を教える〔これは智恵の仕事である〕ことはできず、ただ何かがかくあるということしか教えられない感覚と、智恵とを同一視してはならない」(アリストテレス『形而上学』)。つまり、感覚は火の熱いことは教えてくれるが、なぜ火が熱いかは教えてくれない。「なぜ」という問いに答えてくれるのは智恵である。感覚もたしかに経験のひとつとして知識の出発点にはなるけれども、それだけでは駄目で、智恵への愛が「なぜ」という問いの形で出てこないと、哲学にはならない。そう理解していいだろう。そして、「なぜ」と問うのは、無論、不思議に思ったから、驚いたからであり、「なぜ」と問うとき、人はもう考えはじめている。
疑い
「プラトンやアリストテレスの議論をすべて読んだとしても、示された事物についてしっかりした判断を下すことができなければ、我々は決して哲学者とはならない」(デカルト『精神指導の規則』)。
自分に提供された情報、自分の得た知識を、ただ無批判に受け入れているだけでは、哲学にはならない。それが自分の心から納得できる知識かどうかを、自問することが必要である。その自問は、たとえば近代的な諸科学の成果としての知識が蓄積されてきた17世紀、デカルトによって「懐疑」という形で提起された。自分の得た知識や、自分がその知識を得るのに動員した認識能力等を疑うことを通じて、彼は、すべてを疑ってもなお疑いきれないような確実な真理に到達しようとした。
「私が、すべては偽りであると考えようとしている一方、このように考えている私は当然なにものかでなければならない、ということに注意するやいなや、≪我思う、ゆえに我在り≫という真理が、懐疑主義者の最も無茶な仮定の一切をもってしても動揺させられないほど堅固で確実であることに目をつけ、私はこの真理を自分の求める哲学の第一の原理として、なんの心配もなく認めることができると判断した」(デカルト『方法叙説』)。
ここで疑われているのは、たんに自分の外にあるものだけではない。そもそも自分という人間が本当に実在するのかも、疑ってみていい事柄なのだ。それに、自分の外にあるものも、自分自身にかかわってくるものとして、自分自身にかかわりのある限りでこそ、「疑い」の対象になっている。つまり、この「疑い」そのものが、自分という存在にとって切実な問題であり、さもなければ、それは哲学的な意味を持ちえない。そして、そのような「疑い」が切実な哲学的体験として自分自身の思索を動かすことができるだけの感性がなければ、その人は、ただ疑うために疑っているだけの、たんなる懐疑主義に陥ってしまうだろう。
不安
このデカルトのような疑いを抱いたことのない者でも、ふと自分自身の死を思って、不安にとらわれた経験はあろう。ただ、それがいかにもやりきれない不安なので、それが体験として自分の心に痕跡を残すのを惧れて、すぐに、そのような不安を、また、その不安の種を忘れようとしたのではないか。
けれども、「死を前にしての不安は、最も固有の、他と関連のない、追い出すことのできない存在可能を前にしての不安である」(ハイデッガー『存在と時間』)。
人間は生きている限り、さまざまな可能性を持っている。そのすべての可能性が一挙に不可能になってしまう可能性、それが死であろう。そして、他ならぬ自分の持っている、この死の可能性を、生きている限り、人間は追い越すことも、追い出すこともできない。それが人間を不安にする。「不安が、無をあらわにする」(ハイデッガー『形而上学とは何か』)。
そのような不安を忘れようとするのではなく、逆に、この不安を体験として自分に引き受けるのも、哲学の入り口である。なぜなら、自分が死すべき者として生きていることが自分自身にとってどのような意味を持っているかは、哲学上の大きな、しかも基本的な問題だからだ。ただし、この自分自身の死にかかわる不安から眼をそむけないためには、それなりの勇気が要るはずである。
「哲学たいけん」のために
体験というものは、他人に代わってもらうことはできない。他人にどこまで伝えることができるかも、疑問である。理屈なら、他人に教えることができる。しかし、体験は理屈ではない。どうしても外に表現しきれないところが残るし、その残ったところが、かえって、自分にとっては大きな意味を持っているはずなのである。
自分の心にかかわる主体的な事柄として哲学をとらえるべきだという前提に立って、そのような心に訴える「哲学」的な「たいけん」への導入、あるいはその「たいけん」を媒介としての思索のための示唆を、できるだけ効果的に提供したい、というのが、この「哲学たいけん村」の哲学部門の構想の基本であった。現代のあわただしさが習慣化してしまっている日常生活のなかでは容易には得がたい「哲学たいけん」が、各自の心に訴えかけることで、それぞれの生きていく意味をあらためて考える機縁になれば、というのが、この哲学部門の構想に当たっての願いであった。
ただし、体験というものは、他人に代わってもらうことはできない。他人に押し付けるべきものでもない。体験するのも、その体験を生かすのも、他ならぬ自分自身である。だから、この「哲学たいけん村」でどのような「哲学たいけん」が可能か、また、その体験が今後にどのように生かされるかは、基本的には、この村を訪れる人それぞれにかかっている。
その上でのことだが、この「哲学たいけん村」の発展のための新たな企画や改善の努力を、私たちは惜しむつもりはない。そのためにも、御意見を遠慮なく哲学たいけん村無我苑までお寄せいただきたい。
村長代行・顧問 久野 昭 1992年5月31日 「かわら版哲学たいけん」創刊号より
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 教育部 哲学たいけん村無我苑
電話番号 (0566)41-8522
教育部 哲学たいけん村無我苑にメールを送る
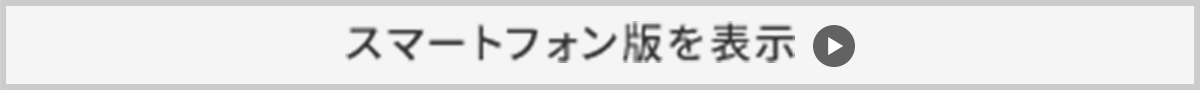







ページID 11300
更新日:2019年06月04日